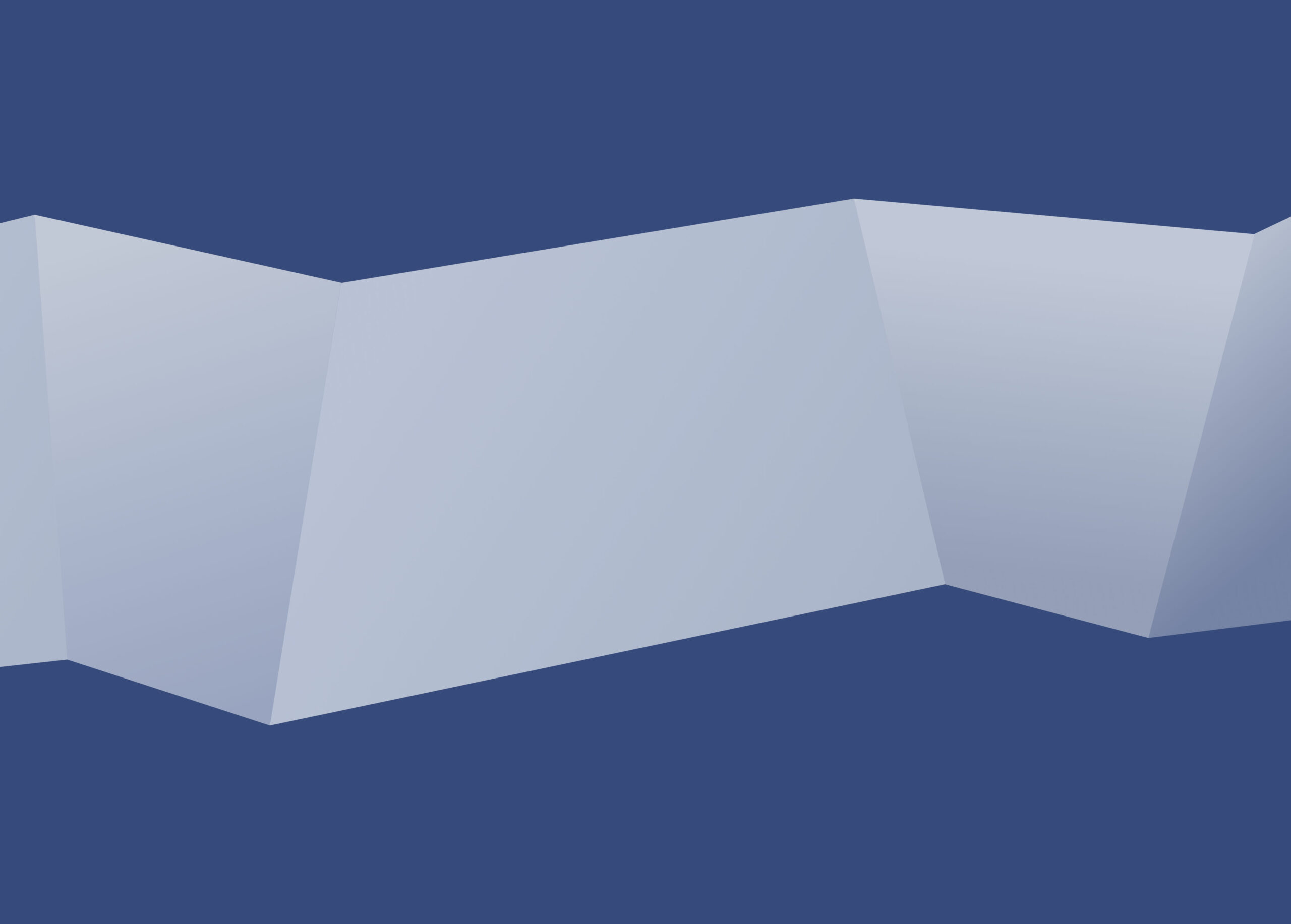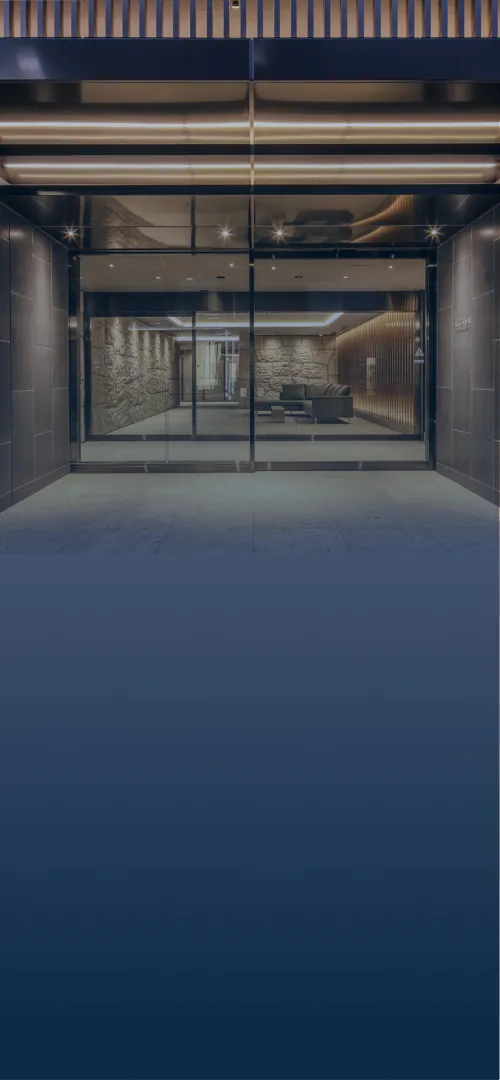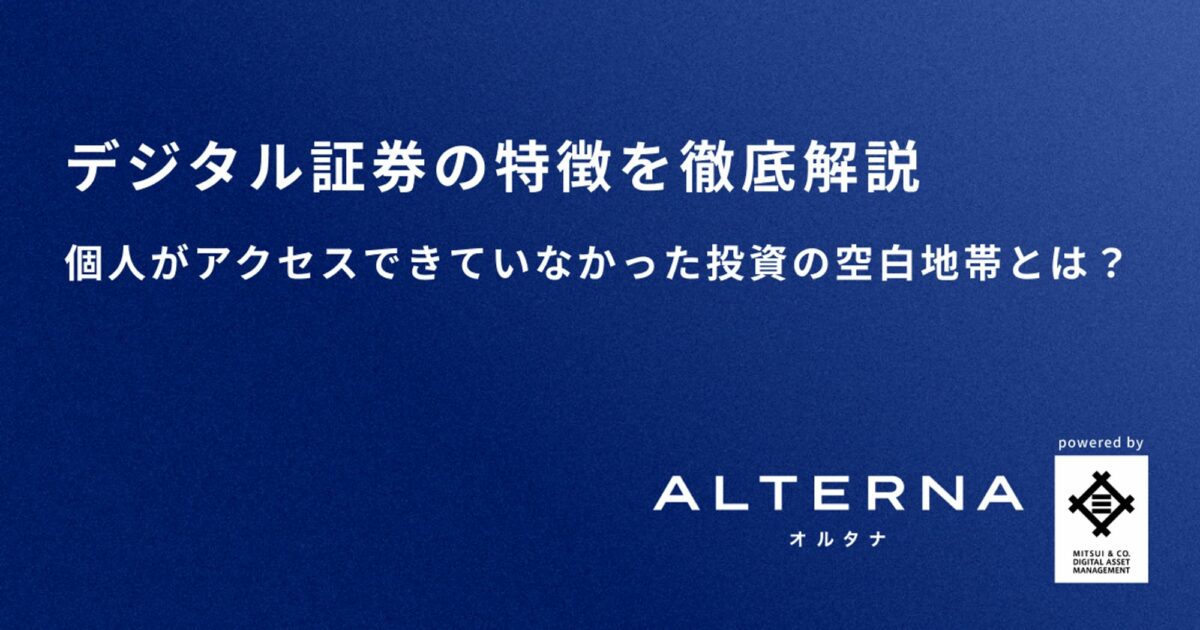コラム・セミナー
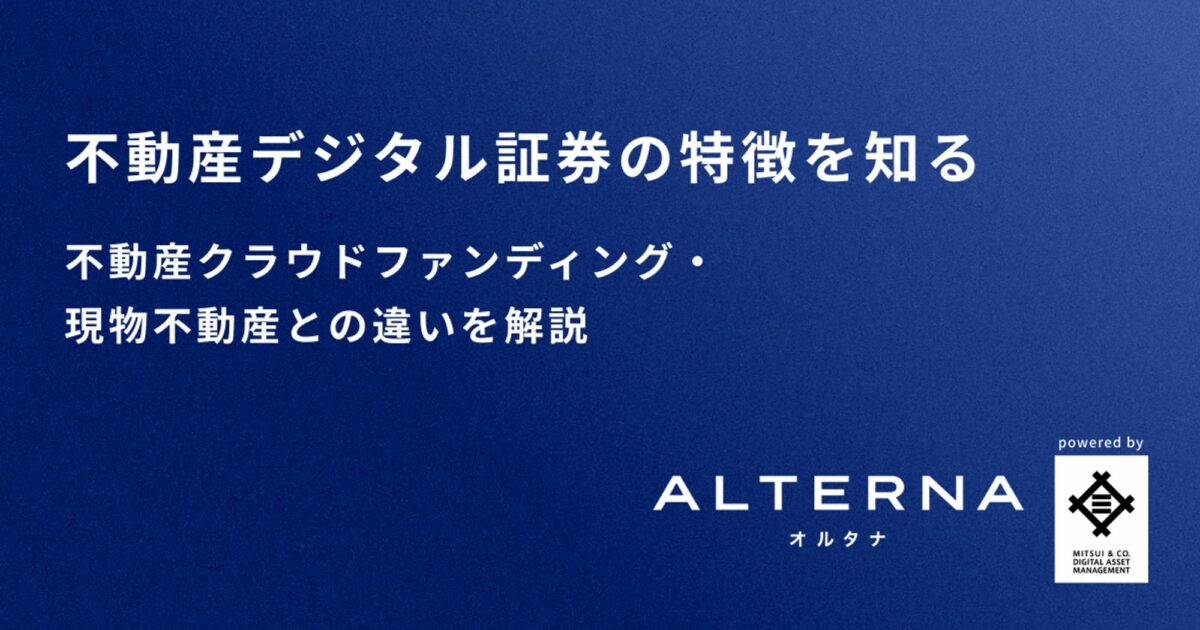
不動産デジタル証券の特徴を知る:不動産クラウドファンディング・現物不動産との違いを解説
はじめに
本記事は、ALTERNA(オルタナ)のLINE公式アカウントに配信された「ALTERNAブログ」の内容を一部編集し、転載されたものです。
この記事に書いてあること
- 不動産デジタル証券と不動産クラファンは小口で不動産に投資する商品であり、個別にお好きな物件に投資ができる点は同じです。
- 一方で不動産デジタル証券の運用期間は5〜7年と比較的長く、かつ税制は、分配金および売却後の譲渡益(発生した場合)ともに申告分離課税の対象である点が特徴です。
- 不動産デジタル証券と現物不動産の違いは投資サイズの差で、投資サイズが大きい現物不動産をローンを組んで投資する場合、その借入利率は相対的に高く、配当原資への影響に注意が必要です。
不動産デジタル証券と不動産クラウドファンディングとの違い
早速ですが、不動産デジタル証券と不動産クラファンとの違いを見ていきましょう。クラウドファンディングには寄付型、購入型などいろいろな種類がありますが、小口で不動産に投資するタイプの不動産クラファンというものもあります。投資対象数が限られることなど、デジタル証券と似た面もありますが、大きな違いは「運用期間」と「税制」です。

不動産クラファンの一般的な運用期間は0.5~1年程度(*)です。中長期の資産形成を行うためには、運用期間の満了のタイミングで新しい商品への再投資を行う必要があります。
(*)当社調べ
一方、デジタル証券の運用期間は5〜7年と比較的中期なため、一度投資した後は一定期間おまかせで運用が可能です。
また、当社で提供予定のデジタル証券は「申告分離課税」という金融商品では一般的な税制が適用されます。

デジタル証券では分配金は約20%(正確には20.315%)が源泉徴収される他、申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の損失と一定期間内の損益通算(損失と利益の相殺による課税対象額の圧縮)が可能です。
一方、不動産クラファンで得られる配当は、雑所得として「総合課税」扱いとなります。年収2,000万円以下の給与所得者で、不動産クラファンからの配当を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、原則として確定申告が必要です。
総合課税の場合、課税所得が330万円を越える際には、デジタル証券で源泉徴収される約20%を上回る課税率(最大時は、住民税とあわせて約56%の課税)となります。また損益通算の対象にはなりません。
※デジタル証券の分配金等が申告分離課税になるのは、不動産デジタル証券として一般的な受益証券発行信託スキームを活用している場合であり、それ以外のスキームの場合は異なる税率が適用される場合がありますのでご注意ください。
不動産デジタル証券と現物不動産との違い
最後に現物不動産との違いについてです。皆さんの中には投資用マンション購入のお誘いを受けたことがある方がいらっしゃるかもしれません。現物不動産投資とデジタル証券の違いは「投資サイズ」と「管理の手間」です。

10万円単位で小口投資ができるデジタル証券ですが、都内の良い立地・築浅のマンション1戸を買うとなれば、最低でも数千万円は必要です。投資サイズが大きいと、自己資金では足りず、投資用不動産ローンを活用している方がほとんどだと思います。物件価格に対する借入額の比率(LTV:Loan To Value)を100%近くにするケースも散見されます。
高LTVであれば、レバレッジ効果で少額の自己資金で大きなリターンに期待ができる代わりに、売却価格が想定通りに達成できない場合には自己資金の回収が叶わず大きく損失を被る可能性もあります。

さらに、個人が利用できる投資用不動産ローンの金利は、住宅ローンに比べ相対的に高く、条件にもよりますがおよそ1.5%〜3.0%といったところでしょうか。またその審査条件も厳しいと言われています。
一方、当社が過去組成したデジタル証券4件の平均LTVは約50%、平均借入利率は1%を下回っています。

つまり、デジタル証券であれば、資産運用会社が投資家の皆様に代わって、銀行から有利な条件でお金を借りてくることに期待ができます。また資産運用会社は、責任をもって物件の運用管理も担います。ローンを組む必要もなければ、ご自身でテナント誘致や物件の品質維持を行う必要もないのです。
まとめ
デジタル証券は、「お好きな優良物件に小口投資」・「手間ひま要らず」・「安定的なリターン」を目指すという特徴を備えた商品だと考えています。